4月に入り、全国各地で桜の便りも聞こえてくる季節になりました。ですが、北の大地、北海道は朝晩に氷点下になる日も。白くなる吐息が冬を名残惜しんでいるかのようです。今回は、取り上げなくして冬の道東を語ることができない「流氷」をテーマに書き進んでいきたいと思います。前回のコラムでは撮りおろしの作品で道東と写真についての考察をしてみましたが今回は2シーズンで撮りためた作品から展開していきたいと思います。

まずは流氷についての紹介です。流氷は一般的にロシアのアムール川の河口で凍った川の水が海に出て風や海流によって北海道のオホーツク海沿岸に到達する海氷のことを指します。海氷と一言にいっても流氷が沖まで来ると波が来なくなるため日本の海岸線で凍った氷もできてくるため交じってしまうと見分けがつきません。氷たちは平和に国際交流をしているのですね。通常1月下旬以降にオホーツク海沿岸の紋別(市が発表)や網走(気象台が発表)などで陸から流氷帯を目視で観測する「流氷初日」と流氷が岸に押し寄せ船の航行ができなくなる「接岸初日」の2つの指標が発表されます。今年は網走で「流氷初日」が観測史上最も遅い2月11日になったことが話題になりました。年々、流氷の厚さや規模が小さくなっているという学術研究もあり、地球温暖化の進行を感じずにはいられません。いまでこそ有力な観光資源として国内だけではなく海外(主に台湾、香港などアジア圏)からの観光客でにぎわっていますが、約60年前まで漁に出られなくなるため厄介者として嫌がられていた存在だったそうです。

ここから被写体としての流氷について考察していきます。自分と流氷との出会いは大学2年生の3月。流氷の見える駅として有名な北浜駅に来たものの接岸していなく、流氷観光砕氷船おーろらに乗って流氷帯にたどり着いた時が人生初でした。海に浮かぶ無数の氷塊にスケールの大きさと異世界を感じたのを覚えています。人生で見るのは最後かもしれないと思うほどで海外旅行先での感覚に近いものがありました。それほど遠い世界だったのです。それから7年が経ちました。縁というのは不思議なもので今や自宅から最寄りの海岸(車で45分ほど)に流氷が押し寄せる環境に変わりました。

今の自分にとって、流氷のとらえ方は大きく3つの視点があります。1つは旅人としての流氷です。ハクチョウなどの渡り鳥も「旅人」ではありますが半日もかからないで海を渡るといいます。それに対して流氷はもっと時間をかけてオホーツク沿岸までやってきます。そして帰らずして海や陸の上で溶けてなくなります。同じ日でも時間によって見えたり見えなかったりする気まぐれなところもチャームポイントかもしれません。
2つ目は「氷」という物質としての流氷です。以前、仕事で流氷の空撮をしたときに一緒にヘリコプターに乗った同僚が上空から眺めた後に「きれいだけど流氷ってただの氷だよね」と言っていたのが印象的な言葉でした。どうしても旅人としてのロマンを一番に感じがちです。もちろんそれはその通りですが、言われてみれば流氷も水が凍ってできたもので、特別な氷というわけじゃありません。移動してくることが特別で氷自体は確かに普通の凍り方です。先述した国内でできた海氷とロシアからの流氷を区別するのが難しいのと同様に区別する意味はあまりないのではないか、とも思ったりもします。物質としての等価性という側面も気になっています。
最後は、流氷の個々のカタチです。ぶつかりあってこすれたり、気温が上がるとぷかぷか浮かんでる最中にぱっくりと割れたりもします。同じ形は2つとしてなく、波に漂い実際に動いて見えるのでまるで生き物のようです。7年前に感動した流氷を「流氷帯」として見るのではなく「個々の流氷」として見ることが環境と時間が変えてくれたことだと思います。
ここで、作品を紹介します。3つのうち最後のカタチにフォーカスした作品群です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「individual」
海に漂い、刻々と形を変える
厳冬期の使者とも言われるが消えゆくさまに心奪われた
1つになったものが溶けて、割れて、形なきものに戻っていく
人々や魂を引き付ける桜の花の儚さとは違う
誰にも個を注目されず、仲間はたくさんいるのに孤独な姿
まるでルールに縛られた社会の中で没個性化していく人々のようにも見えた
冷凍庫のようなオホーツクを溶かしていく春の日差しを受けながら
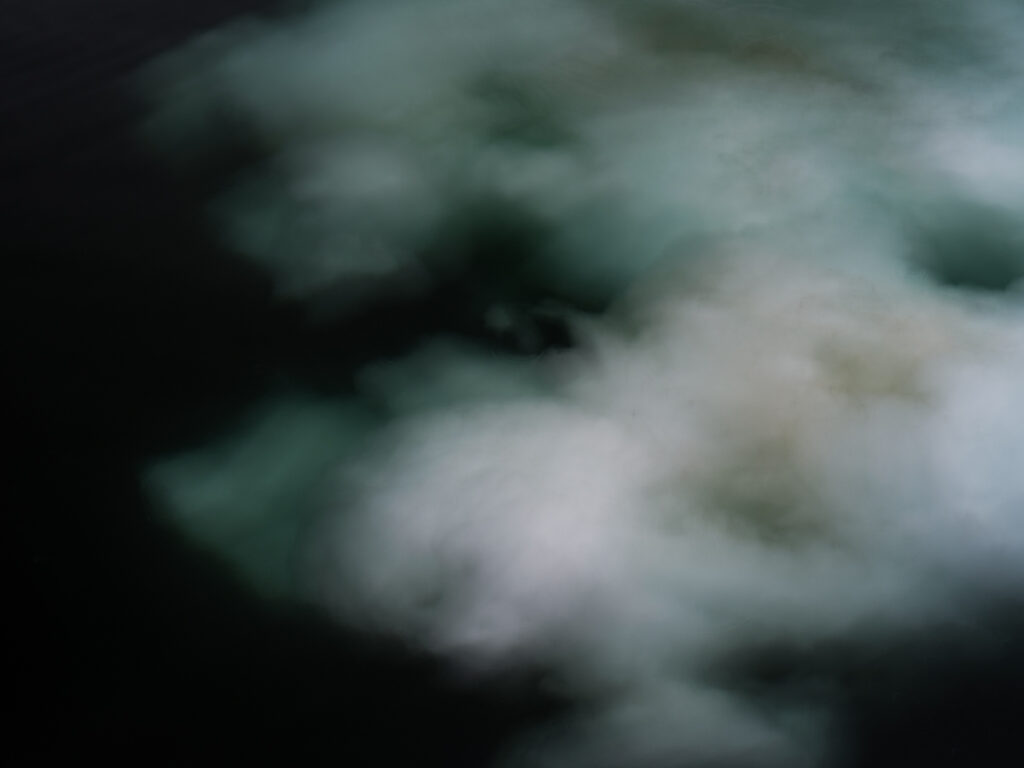





写真には「被写体の魅力や課題を説明する」という力があります。写真メディアが社会に浸透してきた理由はこの力があったからに間違いありません。報道写真はその典型ですし、広告写真やSNSで単発的に大量に流れてくる写真もほぼその特性を持っているといえるでしょう。雑誌やネットの記事に掲載されている写真を見て「行きたいな」と思うことは毎日のようにありますし、当然のことだと思います。ただ、最近「説明する」以外の写真メディアの扱い方をしてみたいという想いが自分の中から離れません。とはいえ、まだ自分の心の中でモヤモヤとしたものが渦巻いていて具体的な姿は捕まえ切れていないのが現状です。今回、北見に来てから2シーズンで撮りためた流氷の写真を全部見返し整理しコラムを書いているなかで「説明する」、それも流氷の特徴的な部分を切り取って自慢げに見せているような撮り方が多くありました。今回お見せした作品にもみられるかと思います。正直「違うな」と。そんな撮り方しかできない自分の力のなさを感じました。おそらく、先に挙げた流氷に関する3つのとらえ方のうち、最後の個々のカタチに対して撮影行為をしていたのかと思います。自分の感覚に正直であるとも言えますが、この撮り方を極めていくことが目指すべき方向じゃないことは感じます。1つ目の旅人や2つ目の物質としての等価性をテーマとして取り上げる具体的なビジョン、手法が見いだせないのは自分の弱さでもあります。
とはいえ、自分が写してきた流氷はまぎれもなく自分の見ている世界観が出ていることは確かです。今の自分が撮れるのは今回お見せした作品です。読んでくださる方に何か伝わることがあれば!、という気持ちは強くあります。「流氷を見てみたい」と思ってくれる人がいたらそれは心からうれしいです。そして、流氷という気まぐれで形を常に変えゆくメジャーな被写体だからこそ気が付けた自分の弱さかもしれません。今は引き出しが少なくても撮り続けることは大事だと思います。来シーズンはよりコンセプチュアルに流氷と向き合えるようにサマーシーズンに精進していきたいと思います。

孤独に解け残る流氷、今はもう海に帰しているだろう=4月4日
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回以降も引き続きよろしくお願いします。

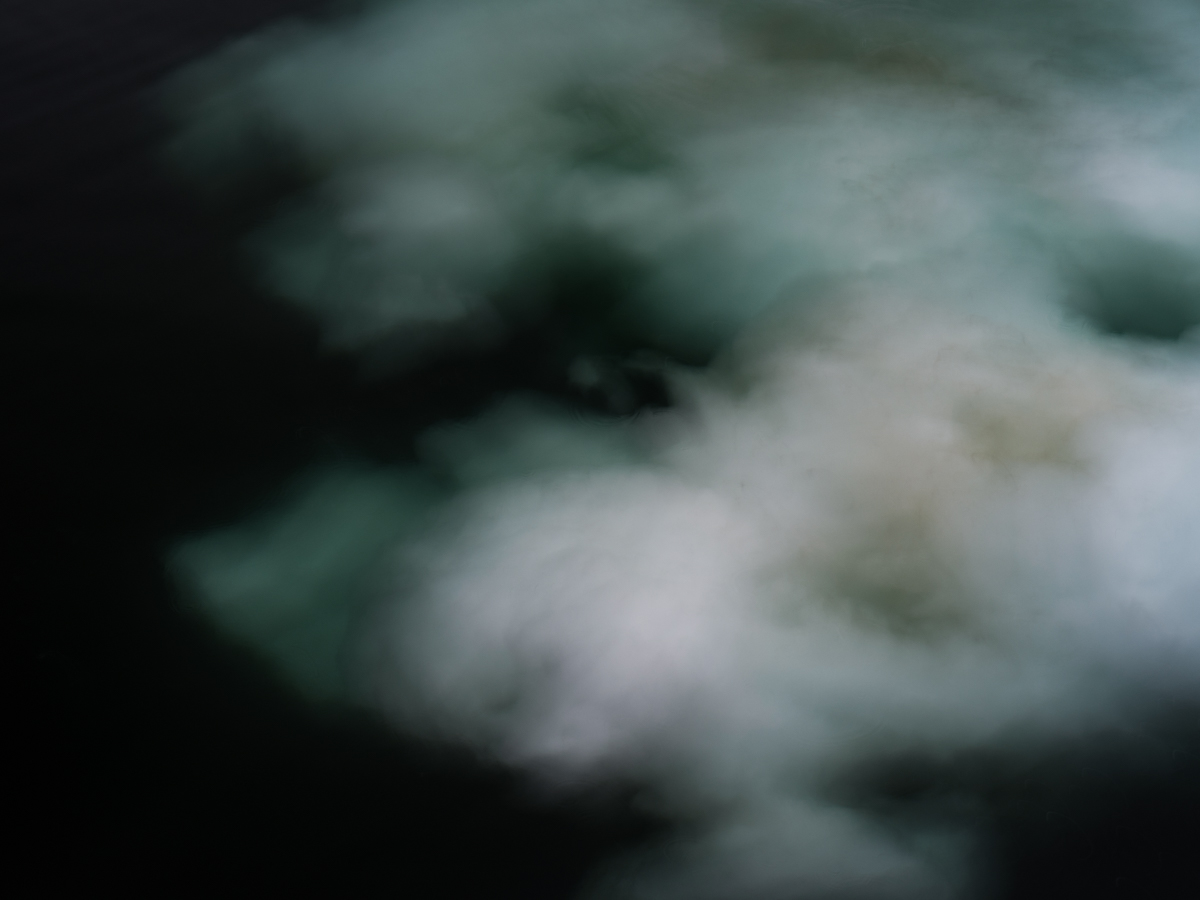

この記事へのコメントはありません。